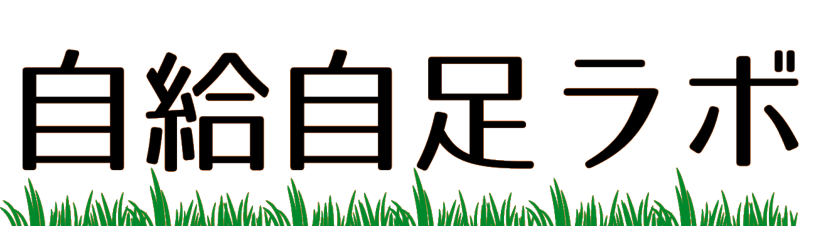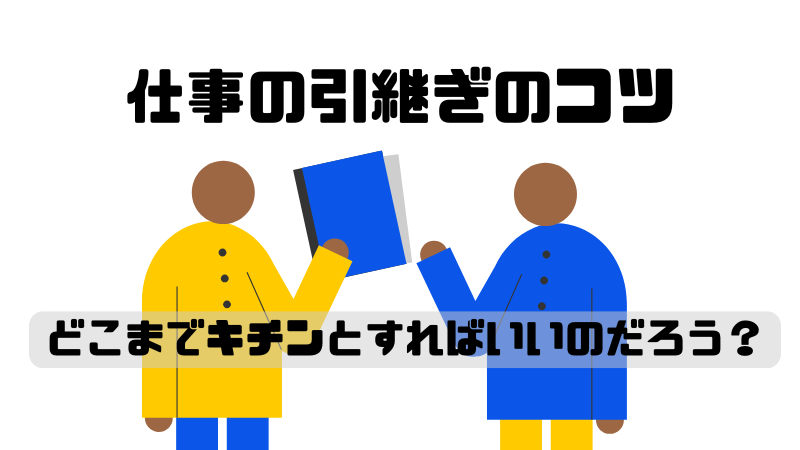組織の中で人事異動があれば、必ず仕事の引継ぎが必要になります。
引き継がなくちゃいけないことが山ほどあるけど、どこまで細かに引き継げばいいのか?
畑違いの部署に異動になって、仕事の引継ぎをうまく受けれるだろうか?
そんな疑問、不安を感じられる方は多いと思います。
サラリーマンをしていれば、人事異動を経験することが一度や二度は、あると思います
公務員となれば、3~5年で畑違いの仕事内容の部署に異動することも珍しくありません。
そんなときの、仕事の引継ぎのコツをお伝えします。
仕事の引継ぎの「あるある」

人事異動があれば、引継ぎをする立場、引継ぎを受ける立場、それぞれの立場で、こんな思いになることは、ないでしょうか?
引継ぎをする立場として、
・仕事内容を全て引き継ぐのは、無理だ。時間が足りない・・。
・この業務は、大事だ。しっかり引き継ぎたいけど、引き継がれるだろうか?
・大量の資料がある。どれも大事な気がする。
・後任者がいい加減な人みたいだ。大丈夫かな?
引継ぎを受ける立場として、
・引継ぎを受けたはいいけど、出来そうにない。不安。ストレス・・。
・いい加減な引継ぎで終わってしまった。どういうつもりだ!
・ぐちゃぐちゃになった資料を引き継いだ。どうすりゃいいんだ?
・前任者みたいにキッチリできそうになり。大丈夫かなー
人事異動と引継ぎ

言うまでもないことですが、仕事の引継ぎは、定年退職や人事異動などによって、仕事をする人が変わることで発生します。
人事異動の目的を掴んでおけば、仕事の引継ぎがしやすくなると思います。
人事異動の目的
そもそも、定年退職や人事異動って、何のためにあるのでしょうか?
同じ人が同じ仕事を続けた方が仕事のノウハウが高まるし、効率的にもなるだろうし、人事異動なんてなければ、楽なのに。と思いませんか?
ある意味では、そのとおりだと思います。
でも、多くの組織では、定期的に人事異動があると思います。
人事異動という仕組みが存在する目的は、色々あると思います。
「適材適所」「人材育成」「モチベーション向上」「不正防止」など考えられますが、ザックリ言えば、「新陳代謝」だと思います。
人事異動と引継ぎ
同じ人が同じ仕事をし続ければ、仕事のやり方が固定化され、新しいやり方を受け入れず、後から来た人が意見を言えず、最終的にはその人は「老害」扱いをされる。という場面を見たという方もいるのではないでしょうか?
そうならないためにも、人事異動があるので、そのタイミングで、一時的に仕事のノウハウが失われたり、仕事の効率が落ちることは、当然だと思います。
もっと言えば、仕事のやり方が変わることを期待されていると考えてもいいと思います。
それどころか、しなくてもいい仕事をやめるキッカケになっていると思います。
だって、新陳代謝のために人事異動しているのに、前任者と後任者がまったく同じ仕事のやり方をしていたのでは、意味がないと思いませんか?
このように考えれば、少し引継ぎのハードルが下がると思います。
前任者のマネをしなくていいと思って引き継げばいいし、後任者に自分のやり方を完璧に引き継ぐ必要はない。と思います。
引継ぎのコツ

仕事の引継ぎについて、ネットで調べると、「引継ぎをスムーズに成功させるために、入念に準備しましょう」という内容のものが多い気がします。
でも、私は、少し違うアプローチでも良いと感じています。
そもそも、膨大な業務を取りこぼしなく、引き継ぐなんて無理です。不可能です。
しっかり引き継ごうとすればするだけ、後任者は、不安になります。
なんせ、無理なことをしているのですから。
でも、まったく何も引き継がないでいい訳でもないと思います。私が、何度も仕事の引継ぎと引き受けをしてきた経験から、いくつかのコツをお伝えします。
引き継ぐ側のコツ
引継書は、シンプルにまとめる。
- 基礎的な仕事の流れを時系列でまとめる。
- 法律的な必須事項など、絶対に漏らせない項目をまとめる。
- やりかけの仕事を一覧表でまとめる。
- 細々とした手順やお作法のようなことまで伝えたくなるかもしれませんが、最小限で伝えればいいと思います。
膨大な資料は引き継がない。
- 自分が大事だと思っている膨大な資料は、後任者にとっては、ほぼ必要ありません。
なにが記載されているか分からない資料は、ないも同然だからです。 - 絶対に捨ててはいけない資料は、自分の責任で、組織内のルールに沿って保管しましょう。
連絡体制を伝える
- 分からないところがあれば、気軽に連絡していい、ということを伝えておく。
要するに、
- 重要なポイントのみ引き継いで、あとは、気になったときに連絡をもらう、というスタンスで良いと思います。
- 完璧な引継ぎをすればするほど、後任者は、前任者に連絡し難くなります。
- 仕事のやり方は、後任者が好きに変えればいい、という考え方の方がスムーズだと感じます。
引継ぎを受ける側のコツ
当面の仕事の流れを確認する
- 右も左も分からない職場に異動するときに、何をしてよいのか、さっぱり分からないということでは、さすがに困ります。
- 目の前にある、仕事の流れぐらいは押さえておいた方が安心です。
とりあえず、今後1~2カ月の間にすることを確認するという感覚で乗り切れると思います。
膨大な資料を受け取ったら、とりあえず放置する。
- 膨大な資料に目を通している暇はありません。一旦、邪魔にならない場所に放置しておきます。
1年ぐらい経って、仕事の流れが分かった時点で、その資料を見ることがなければ、ノールックで捨ててしまいます。 - リサイクルするなら、クリップぐらいは外しましょう。
前任者の連絡先を確認する。
- 分からないところは、連絡させてもらうような話をしておけば、連絡できるという安心感につながります。
- でも、余程のことがない限り、連絡することはないと思います。私の経験上、過去の経緯をどうしても知らなくちゃいけないトラブルの場合のみ連絡したことがあります。
要するに、
- 目の前にある当面の仕事だけ確認しておけばよいと思います。
- 細々と引継ぎを受けると、そのとおりにしなくちゃいけないという状況になるので、細かなことは、聞かない方がスムーズだと思います。
私の経験

私自身は、公務員として約25年間仕事をしてきて、畑違いの人事異動を何度も経験しました。そんな人事異動を繰り返す公務員だからこそ、引継ぎを多く経験してきました。
そんな経験が、参考になるかもしれません。
「こんな引継ぎでも、仕事は回るんだ」と感じていただければと思います。
初めての人事異動(引継ぎを受ける立場として)
初めての人事異動は、申請受付等の担当課から、その部門の総括部署への異動でした。
仕事の幅が広がったので、面白そうだと感じましたが、総括部署なので、とにかく庶務業務の種類が多いところです。
異動内示から、異動までが3日程度しかない中で、2~3時間で引継ぎを受けました。
目の前の仕事の流れの説明を受けて、「詳しい内容は、この本を読んで勉強してね」という引継ぎだったと思います。
異動して出ていく方は、ご自身の移動先の仕事に気持ちが行ってしまっているので、引継ぎをさっさと終わらせてしまうという状況でした。
少し不安に感じつつも、業務スタートしてしまえば、引継ぎが薄かったこともあり、仕事のやり方を自由に変えれたので、はっきり言ってやりやすかったです。
畑違いの人事異動(引継ぎを受ける立場として)
公共事業関係部門への異動でした。
今まで、図面も見たことがない、設計もしたことがない、というド素人にもかかわらず、工事を発注するような部門に異動してしまいました。
異動初日から、「あなたの担当事業は、この一覧だから、よろしくね」という引継ぎとは言えない、ただの業務分担表を渡されただけで、スタートしました。
はっきり言って、腹が立ちました。「できるわけ、ないじゃん!」。嫌がらせじゃないかとも思いました。
とは言え、そうも言っていられないので、周りの人に助けられながら、どうにかこうにか、仕事を進めました。
はじめて使うCAD、はじめて使う工事積算システム、初めて作る設計書。こんなド素人でいいのか、と疑問に感じながら、数年間を過ごしました。
割り切って考えれば、生まれながらに何かの専門を持っている人間なんていません。
その場に合わせて、必要なノウハウを学べばよいだけのことです。
職場唯一の立場の仕事の引継ぎ(引継ぎを受ける側する側、両方の立場として)
ある部門の中で、その職場の中で唯一の役職の仕事を、前任者から引き継いで、数年後には、後任者に引き継ぐという状況でした。
引継ぎを受ける側の立場の時には、
1~2時間程度の引継ぎでした。
他の同僚に頼れない業務の流れについて、引継ぎを受けました。
同時に、段ボール10箱分ぐらいの資料も引継ぎを受けました。
後は、やりながら慣れていくという状況でした。
前任者の方は、こと細かに引き継ぐと、やり難くなることを見越していたようで、「一応、自分はこうしていたけど、自分のやり易いように変えていいと思うよ」というスタンスの引継ぎでした。
ということで、遠慮なく、仕事のやり方を自分がやり易いように変えることができました。また、しなくてもいいかなと思うことは、あっさり簡略化しました。
引き継いだ膨大な資料は、何が入っているか把握できなかったので、ないも同然と思って、1年間寝かせたのちに、半分ぐらいは、中身を見ることもなく捨ててしまいました。
引き継ぐ立場の時には、
前任者から引継ぎを受けた時と同様のスタンスで引き継ぎました。
業務の流れとスリム化した資料を引き継ぎました。
その後任者は、1年後には、さらに業務を簡略化して、資料もほとんど捨てていました。
資料は、分かりやすいようにした方が良いだろうと思い、インデックスをつけたりして整理したつもりではありますが、あっさり捨てられてしまいました。
なんか、あっさりしていていいな、と思います。
気合を入れて、資料を整理して引き継いでも、引き受けてくれるとは限らないということですね。
まとめ

「しっかり引継ぎを受けなくては!」と焦っても、完璧にできるわけありません。
「この仕事は大事だから、しっかり説明しなくては!」と意気込んでも、後任者には伝わりません。
人事異動の大きな目的が「新陳代謝」だと思えば、仕事の引継ぎを気負う必要など、まったくない、と感じます。
自分が大事だと思っている仕事は、自分だけが大事だと思っている仕事だということは、よくあります。
人によって、引継ぎ内容の濃淡はあると思いますが、この記事の内容を一つの目安にしていただければ、気負わずに仕事の引継ぎを乗り越えられると思います。