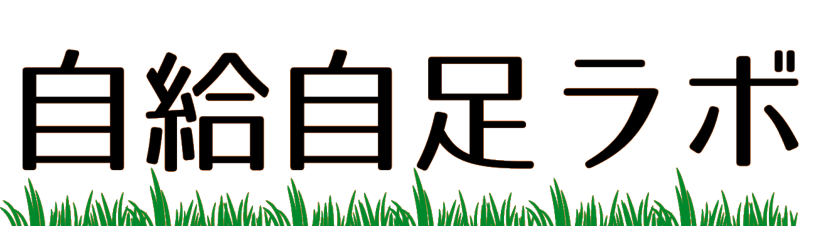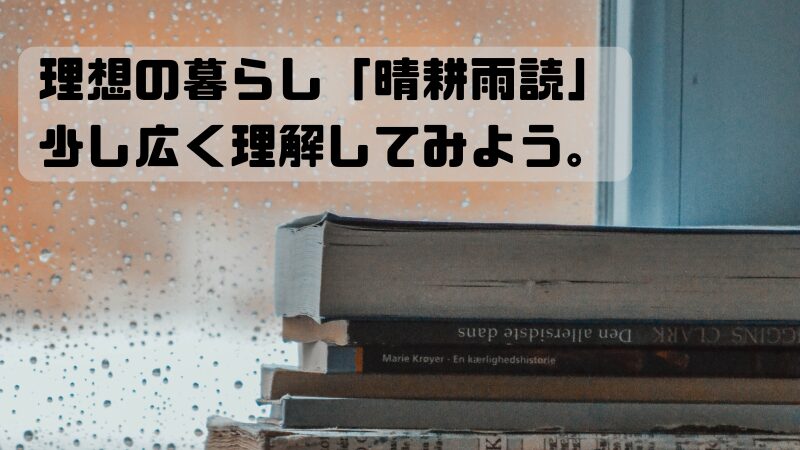「晴耕雨読」とは、どのようなイメージでしょうか?
単に悠々自適な暮らしのことを指している言葉なのか、それ以上の意味のある四字熟語なのか。
私自身、自給自足で晴耕雨読という、悠々自適な暮らしに憧れているので、その意味を広く理解してみることにしました。
辞書での定義

晴れた日には田畑を耕し、雨の日には家にこもって読書をすること。悠々自適の生活を送ることをいう。
引用:Weblio 辞書 デジタル大辞泉
雨が降れば家の中で、読書で過ごす。
華やかではないけど、ストレスのない、ちょっと世間からはずれたところで暮らしている。
まさにスローライフ、悠々自適というイメージです。
憧れる人が多い生活だと思います。私も、こんな生活に憧れます。
そもそも語源は?

はっきりとした語源は分からないようですが、いくつかの説があります。
塩谷節山(1878年生 東京帝国大学、漢学者)という方が明治時代に書いた漢詩の中に「晴耕雨読優游するに足る」という言葉があるようです。
伊藤左千夫(1864年生 歌人、小説家)という方が明治時代に書いた短編小説「紅黄録」の中に「晴耕雨読」という言葉があるようです。
明治時代以前には、「晴耕雨読」という言葉が見つからないようなので、そんなに古い言葉ではないように感じます。
私の考えですが、「晴耕雨読」という言葉が近代になって、取り上げられるようになったということは、それ以前は、晴耕雨読の暮らしが理想だという考え方が、なかったのではないかと感じました。
近代になって、日々の暮らしに余裕がなくなり、慌ただしい生活から逃れたいと考える人が増えたことからスローライフ的な暮らしを理想に感じる人が増えたことで、「晴耕雨読」という言葉が登場したのかな、と想像しました。
四字熟語として、別の意味も
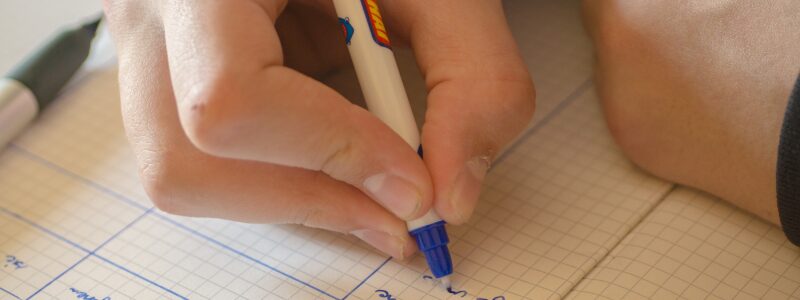
「晴耕雨読」と聞いて、最初に思いつくイメージは、辞書での定義どおり、悠々自適な暮らしというイメージですが、四字熟語として、他の意味もあるようです。
例えとして、よく出てくる話は、三国志で有名な孔明の話です。
ざっくり言うと、
孔明は、劉備に迎えられる前、晴れた日には畑仕事で体力維持して、雨の日には知識を蓄えるために読書に励むという、大きなことに当たる前の準備となる暮らしを送っていた。飛躍する前に、必要な体力と知識を蓄えていた。
ということのようです。
辞書での定義だと悠々自適な定年退職後の老後の生活のようなイメージですが、孔明の例によると、こらから社会に出ていく学生時代のよに、きっちり体力をつけて、勉強に励んでいるような、準備段階のイメージに感じます。
暮らしぶりとしては、似たような面がありますが、ちょっと想像してみるだけで、心持ちが全然違います。
禅語でもある

晴耕雨読は、禅語としても取り扱われています。
禅語による考え方を読んでみると、「晴耕雨読」には、さらに広い意味があるように思います。
晴や雨を「気持ちの状態」として考える
「晴」と「雨」を心の状態としてとらえると、単に暮らしぶりを表す意味ではなくなります。
気持ちが晴れているときには、外に出て働き、
気持ちが雨の時には、自分の心を読みながら、ゆったりする。
という、「気持ちが晴れないときには、無理をしない。」という意味にもなります。
晴や雨を「自分の周辺環境」として考える
「晴」や「雨」を自分の周辺環境としてとらえると、置かれた状況にどう対応するのかという心得のような意味にもなります。
経済状態や組織内での立場が良い時(晴のとき)にはしっかり働いて生活の糧を得る。
立場が恵まれない時(雨のとき)でも、無気力にならず、無理をせず自分にできることをする。
という、「置かれた状況に応じて、できることをする」という意味にもなります。
まとめ
「晴耕雨読」といえば、スローライフのイメージですが、色々な意味も考えられますね。
私としては、スローライフのイメージを持ちながら、気持ちの状態や置かれた立場が雨の場合でも、自分にできることを無理をせずに続ける。という意味もプラスしていきたいと思いました。
「人間らしく生きる」という意味でとらえておこうと思います。