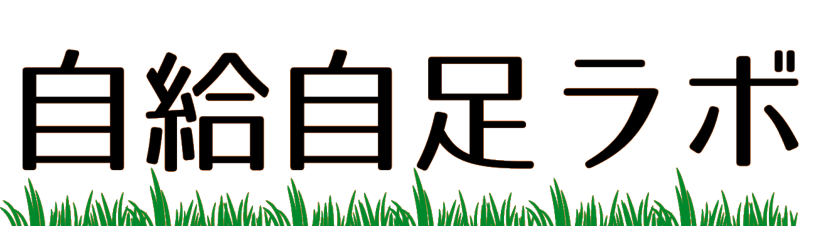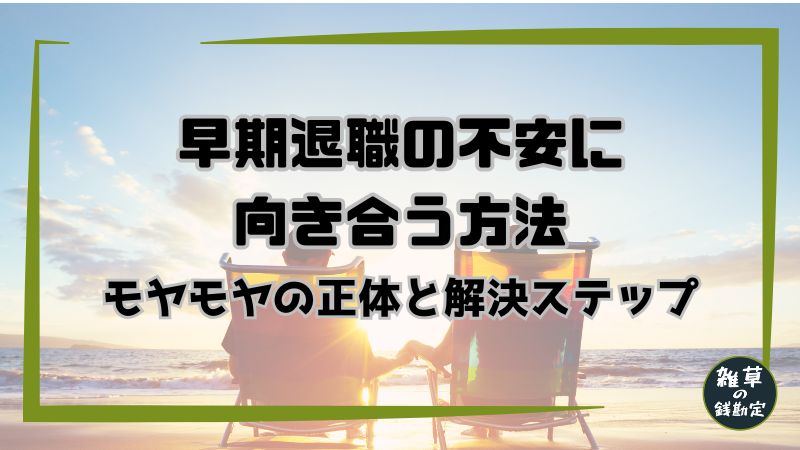「早期退職したい。でも不安がつきまとう。」
そんなモヤモヤした気持ちを、ひとりで抱えていませんか?
- このまま辞めてしまって、生活できるのか?
- 家族に反対されそうで言い出せない。
- そもそも辞めた後、何をすればいいのか?
僕は、50歳手前で早期退職しましたが、早期退職を考え始めたときは、やはり、不安を感じていました。
そして、その不安が漠然としたままだった時期には、次の一歩を踏み出すことは、できませんでした。
また、早期退職というのは、人生の中でも大きな転換点です。
気軽に同僚や家族に相談できるものではありません。
この記事では、早期退職したいと思いながら、漠然とした不安を感じて動き出せないでいる方に向けて、その不安の正体と解決ステップについてお伝えしようと思います。
早期退職に関連する「不安」の正体
お金の不安:「退職後、生活していけるのか?」

まず最も大きな不安は、やはり「お金」です。
- 毎月の生活費はどのくらいかかるのか?
- 退職金と貯金だけで、年金受給まで足りるのか?
- 子どもの教育費や住宅の修繕の見通しも立たない…
これらが明確でないまま、「仕事を辞めたい」という気持ちだけが高まっても、具体的な行動を起こす気には、なかなかなれないと思います。
具体的な金額を把握する必要があります。
例えば、老後資金について、公的機関から出されている情報を整理してみると、以下の通りです。
| 出典(公表日) | 老後資金の必要額目安 |
|---|---|
| 金融庁 金融審議会報告書「高齢社会における資産形成・管理」(2019年6月3日公表) | 約1,300万~2,000万円 (老後生活費と年金額の差額から試算) |
| 内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」結果 (令和6年度調査・2024年公表) | 平均約2,648万円 (60歳以上の男女へのアンケート調査結果) |
この他にも、民間機関の調査でも老後資金は、2~3千万円必要という情報が多数あります。
また、SNS上では、「○億円ためて、FIREしました。」という投稿を目にすることもあります。
【解決のヒント】
これらの情報は、参考になりますが、自分自身の状況とは一致することはありません。
自分自身に置き換えて考えるためには、「生活レベル」「都市部と田舎」「持家と賃貸」「家族構成」など、様々な要因を考える必要があります。
不安を少しでも解消するためには、ネット上の情報を参考にしながらも、自分自身のマイプランを作る必要があります。
家族の反応:「理解してもらえないのでは…?」

「仕事を辞めたい」と家族に伝えたと想像してみてください。
色々な反応が予想されます。
- 「生活どうなるの?」
- 「子どもの教育費はどうするの?」
- 「辞めて何するつもりなの?」
早期退職の話題は、”地雷”になる可能性があります。
そして、家族の理解が得られないことは、自分自身の大きなストレスになる場合もあります。
家族の反応を想像すると、気軽に話してみることに躊躇すると思います。
気軽に話題にして、一蹴された経験をお持ちの方もおられるかもしれません。
【解決のヒント】
夫婦間の関係性、お互いの仕事の状況などもあり、コレという解決策はないのが現実だと思います。
あるとすれば、「きちんと話す」ということに尽きます。
パートナーの疑問や不安にきちんと答えるように、具体的に話していく必要があると思います。
おそらく、お金に関する不安が話題の中心になると思いますので、パートナーの気になる部分も含めたお金に関するマイプランは、必須になると思います。
社会的な不安:「会社を辞めた後の“正体不明な自分”」

仕事を辞めた後に、自分が何をしているのか、具体的に想像できている方は、比較的少ないのではないでしょうか。
組織で働き続けることに違和感を感じて、早期退職したいと考えている方でも、ほとんどの場合、退職後の生活は漠然としていると思います。
- 仕事を辞めた後、日中何をして過ごすんだろうか?
- 無職の中年なんて、社会から必要とされないのでは?
- 家庭の中で、どんな役割を果たせばいいのだろう?
特に、若いころから、組織の中で懸命に働き、それなりの評価を得てきた方ほど、辞めた後のビジョンを描き難いと思います。
組織の看板、役職、家庭内での立場、これまでの自分の存在を形作ってきたものが、一気になくなってしまうから、当然です。
【解決のヒント】
早い時期から、退職後の具体的な生活をイメージして、準備を進める必要があると思います。
(これは、早期退職でも、定年退職でも同じことだと思います)
- 理想の暮らしをイメージする。
- 自分の強み、得意なことを言語化しておく。
- 退職後の仕事づくりの準備(副業活動など)を進めておく。
- 家事ができるようにしておく。
することはたくさんあります。
興味のあることからでもスタートすれば、退職後が少しづつでもイメージできてくるはずです。
不安の正体を“言語化”すると、対策が見えてくる
「なんとなく不安」を分類してみる

「辞めたいけど不安」というモヤモヤは、分類してみることで、冷静に向き合うことができます。
| 不安を考える視点 | 具体的な例 |
|---|---|
| お金 | 生活費、医療費、教育費、 退職金、年金、収入減など |
| 人間関係 | 家族の反応、夫婦関係の変化、 同僚の反応、周囲の目など |
| 自分自身 | 退職後の活動、家庭での役割 孤独感、アイデンティティ喪失など |
様々な視点から、不安に感じることを具体的に見える化していくことが、解決への行動につながる出発点になります。
少しでも気になることは、書き出して言語化していくのがお勧めです。
不安には事前準備が「できるもの」と「できないもの」がある

不安を見える化してみると、その不安の中には、
“事前に向き合って解決できるもの” と
“事前に考えすぎてもしょうがないもの” があります。
例えば、
- 老後の生活費が不安
⇒事前に向き合って、プランを作ることで安心につながる。 - 家族に反対されそうで不安
⇒家族に相談してみたら、意外と「応援するよ」と言われた。
書き出した不安を仕分けするだけでも、まず何から向き合えばいいのか、見えてきます。
事例から学ぶ、「早期退職」の準備

事例とは言っても、僕自身の事例です。
僕の場合は、50歳手前で、公務員を早期退職しました。
辞める数年前から漠然と早期退職は考えていましたが、本格的に考えだしたのは、約1年前です。
どのような不安に、どのように対応したのか、参考にしてください。
お金の不安は、プラン作成で解決
最も大きな不安は、お金に関するものでした。
我が家の家計の収入の柱は、僕の給料収入だったので、それがゼロになった場合には、子どもの教育費、住宅ローン、老後の生活など、様々なことが不安になります。
早期退職を家族に相談するためにも、具体的な数字として見せる必要があると考えたので、ライフプランを作ることにしました。
このプランを自分自身で作ることで、家計の状況も把握することができました。また生活費の節約をする意識も高まりました。
退職後の自分自身の活動や役割
僕自身は、もともと料理を含め、家事が得意だったため、家庭内では主夫という立場を担うことにしました。
また、自給自足的な暮らしにも興味があったので、主夫という立場の中で、畑仕事や節約も楽しみにしていました。
さらに、このブログやメルマガを通じたフリーランスとしての活動も本格的に進めたいという思いがありました。
ということで、退職後は、とりあえず、自給自足に挑戦する主夫兼フリーランスという立ち位置で、生きていくことにしました。
得意なことや好きなことをベースにして、自分の役割を決めたうえで、退職後の暮らしがスタートしたので、幸いなことに「することがない日」というのがありません。
周囲との関係
早期退職するためには、家族や同僚に話をしていく必要があります。
僕の場合には、以下のように話を進めました。
- まず、妻に相談
家計を一緒に担っている妻には、「相談」という形で話をしました。
事前にライフプランを作っていたので、その内容も話をすることで、妻が不安に思うポイントも聞き出すことができ、それをプランに反映させて、具体的な話ができました。
最初は、「えー!、まじで」という反応でしたが、最終的には「まあ、いいんじゃない」という理解を得るに至りました。
- 職場の上司に報告
職場の上司には、「報告」という形で話をしました。
仮に相談という形で話をすると、「考え直すように」という結論になることが想定されるので、「報告」のスタンスで話をしました。
それでも、引き止められましたが、何度か話をして、スムーズに理解を得ることができました。
- 親への報告
僕自身の親には、割と退職の直前に「報告」しました。
親への話し方は、人それぞれの関係性で、話す時期や話すスタンスも変わってくるんだと思います。
反省点と振り返り
- 反省点
反省点は、退職後の自分の活動の準備が思うように進めることができていなかった。という点です。公務員であったために、当然「副業禁止」だったので、かなり自制した準備しか進めていませんでした。
今思えば、もっと準備を進めても問題なかったと思いますが、今から頑張るしかないと思っています。 - 振り返り
お金に関するライフプランを作成しておいたことは、不安解消にもなると同時に、家族と話をする場面でも役に立ちました。
早期退職は、人生の大きな転機でもあるので、ライフプランを作っておくことは、意味のあることだと感じています。
不安を和らげる準備のすすめ

お金の不安に向き合うことで、大きな不安は消える
多くの方にとって、早期退職の最大の不安は、「お金」だと思います。
現実的な生活費、貯金、退職金、年金などを「具体的な数字」で見える化してみることで、”漠然”とした不安が”具体的”になってきます。
- 今後必要な支出を洗い出す
- 退職金、年金受給額、貯蓄額を具体化する
- 早期退職の具体的なスケジュールを考える
数字で確認できれば、「足りないなら何をするか」「足りているならいつ辞めるか」が明確になります。
まずは、「辞めたい」気持ちに向き合う
お金の不安に向き合うことは、具体的に早期退職を考えるときには、避けて通れないものだと思います。
でも、まずは、「定年まで勤めるのはしんどい」「早期退職したい」という気持ちに向き合うのが大事なことだと思います。
そんな方のための無料メルマガ講座も準備しています。
無料ですので、気軽に登録していただければと思います。
※この記事の下の方から登録できます。
まとめ|不安は「辞めたい気持ち」が本気の証拠
「辞めたいけど、不安で踏み出せない」
その不安があるということは、現実をちゃんと見ようとしている証拠です。
「不安だから諦める」ではなく、
「不安だから向き合ってみる」ことで、
きっと、後悔のない選択につながると思います。